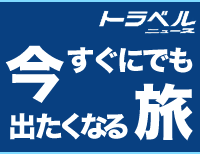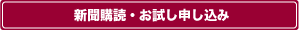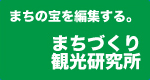子どもと出会いまちの風土知る 福岡・秋月
08/01/15
「こんにちはー!」
福岡県朝倉市の秋月城跡に明るい子どもたちの声が響く。福岡県商工部国際経済観光課が11月、関西、中京圏の記者を招き、筑前・筑後の町並みを見て歩いた。秋月城跡では、遠足に来ていた近隣の小学生と出会った。
こちらから声をかける前に、自分からあいさつしてくれる子どもたち。中には「どうぞ」とお菓子を分けてくれる子も。あまりのストレートさと最近見かけることが少なくなった光景に正直、面食らったが、すごくうれしい。

秋月城址の広場を子どもたちが元気に走りまわる
秋月は、筑前の小京都と呼ばれる城下町。鎌倉から江戸時代に栄えた城跡周辺の町並みや特産のスイゼンジノリが観光資源だ。
ボランティアガイドを務める三浦良一さんは、元地元中学校の校長。「秋月には派手なものはありません。ですが、秋月藩ゆかりの歴史文化や昔ながらの人情が残っています。ゆっくり歩いて風土に触れることで、自分なりの魅力を発見してほしい」と話す。
―はい、もう見つけました。
柳川市で11月1日に開かれた郷土ゆかりの文人、北原白秋の命日を偲ぶ「白秋祭水上パレード」でも同じような場面に遭遇した。掘割をどんこ舟と呼ばれる船で進んでいくと、行く先々で「こんばんわー!」「ようこそ柳川へ!」「どこから来たの?」と声が飛ぶ。声の主は、子どもを中心とした柳川の人たちだ。掘割沿いで披露される郷土太鼓や白秋の童謡の合唱などにとどまらない。「自分たちも客をもてなそう」という風土が根付いているまちなのだろう。船上の我々と掘割沿いの子どもたちのやりとりは、船が離れるまで延々と続いた。
同行した記者は、口々に「いつ以来だろうね、こんな感覚は」「これが旅本来の良さじゃないか」。
―うん、迷わずうなづいた。